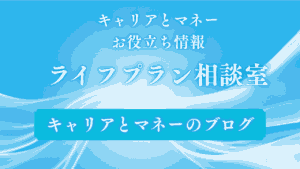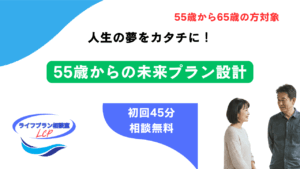第一章:見えない壁
またか・・・
スマートフォンの画面に表示された「お祈りメール」の定型文を、私は無感情に見つめていた。これで、何社目になるだろうか。指で数えるのも億劫になるほど、同じ光景を繰り返していた。
私の名前は真田慎二、53歳。中堅の電子部品メーカーで30年、技術者として、そしてここ10年はマネージャーとして、ひたすらに走り続けてきた。心血を注いで開発した製品が市場に出回り、会社の成長に貢献してきた自負はある。部下を育て、チームを率いて、いくつもの困難なプロジェクトを成功に導いてきた経験もある。
だが、50歳を過ぎたあたりから、心の中にぽっかりと穴が空いたような感覚が居座り始めた。このままでいいのか? 定年までの残り時間を、ただ同じサイクルの繰り返しで終えるのか? 人生の集成として、これまで培ったスキルを、もっと直接的に社会の役に立てるような、手応えのある仕事がしたい。そんな青臭いとも言える情熱が、日に日に大きくなっていった。妻の明子も「あなたの人生だもの。悔いのないようにしたらいいわ」と背中を押してくれた。
こうして、私の「セカンドキャリア」への挑戦は始まった。
転職エージェントに登録すると、私の経歴は意外なほど高く評価された。同業他社はもちろん、異業種のコンサルティングファームや、技術顧問を求めるスタートアップからも声がかかった。書類選考の通過率は、自分でも驚くほど高い。
問題は、その先だった。
面接、特に役員クラスが出てくる最終面接で、必ず壁にぶち当たるのだ。手応えは、ある。これまでの実績を語れば、面接官たちは一様に頷き、メモを取る。技術的な質問にも、マネジメントの要諦についても、よどみなく答えているはずだ。だが、面接が終わる頃になると、彼らの目に、ほんのわずかな曇りが生じるのに気づく。その曇りの正体がわからないまま、数日後、不採用の通知が届く。
「ラストワンマイル問題」――エージェントの担当者はそう言った。ゴールテープの目前で、なぜか足がもつれて転んでしまう。そんなもどかしい状況が、もう半年近く続いていた。
「どうしてなんでしょうね…」
電話口で弱音を吐く私に、担当者は言葉を選びながら言った。
「真田さんのご経験は素晴らしいものです。ただ…そうですね、少しだけご自身の経験に絶対的な自信をお持ちなのが、時として…その…」
言葉を濁されたが、言わんとすることは痛いほどわかった。「傲慢」「上から目線」。そう見られているのではないか。面接官の多くは、私より一回りも二回りも若い。彼らにとって、自信満々に過去の実績を語る53歳の男は、扱いにくい「おじさん」にしか見えないのかもしれない。
そんな不安が頭をもたげると、面接での受け答えが、どんどん窮屈になっていく。経験を語れば「自慢話」と取られ、謙遜すれば「自信がない」と思われる。正解がわからない迷路に、私は完全に迷い込んでいた。
ある夜、リビングで一人、缶ビールを呷っていると、明子がそっと隣に座った。
「また、ダメだったの?」 「……ああ」 「あなた、最近ずっと難しい顔してるわよ。昔のあなたは、もっと楽しそうに仕事の話をしてくれたのに」
妻の言葉が、乾いた心に染みた。そうだ、私はいつからこんなに必死で、不機嫌な顔をしていたのだろう。転職は、もっと前向きな挑戦だったはずなのに。
「どうしたらいいのか、わからなくなってきたんだ」
弱音を吐くと、明子は私の手元にあったタブレットを手に取り、何かを検索し始めた。そして、一つのウェブサイトを私の前に差し出した。
「こういうのは、どう?」
画面には「ネクストキャリア・ラボ」という文字が躍っていた。ミドル・シニア層に特化した転職支援サービスらしい。数十万円もする包括的なコンサルティングではなく、「最終面接を突破する」という、まさに私の抱える「ラストワンマイル問題」に特化したプログラムが、6万か8万で受けられるという。
――AI活用 面接力診断。
その文字に、私の目は釘付けになった。AIか。機械に、この俺の何がわかるというんだ。半信半疑の気持ちと、藁にもすがりたい思いが交錯する。しかし、このまま同じことを繰り返しても、結果は目に見えている。
「…試してみるか」
深夜、私は意を決して、その診断サービスに申し込みのボタンを押した。自分でも気づいていない「何か」を、この無機質なテクノロジーが見つけ出してくれるかもしれない。そんな淡い期待を胸に抱いて。
第二章:己を知る
数日後、オンラインで行われた「AI活用 面接力診断」は、想像以上に本格的なものだった。指定されたウェブ会議システムにログインすると、画面の向こうに柔和な表情の男性が現れた。「ネクストキャリア・ラボ」の代表であり、2級キャリアコンサルティング技能士の国家資格を持つという中島さんと名乗る人物だった。
AIによる模擬面接が始まった。画面に表示される質問に、私はいつものように、しかし少しだけ意識して丁寧に答えていく。自己紹介、実績の説明、困難を乗り越えた経験。30分ほどの面接が終わり、しばらくして診断結果が画面に表示された。そこに書かれていた言葉に、私は息を呑んだ。
【あなたの隠れた課題】
- 経験を伝える際の柔軟性に欠ける印象
- 戦略的思考の欠如(技術的な「What」を語りすぎる)
頭をガツンと殴られたような衝撃だった。「柔軟性に欠ける」。それは、自分では最も遠い言葉だと思っていた。私は常に新しい技術を学び、部下の意見にも耳を傾けてきたつもりだ。
「納得がいかない、というお顔ですね」と、画面越しの中島さんが静かに言った。
「この診断は、AIと私のダブル評価で行います。まず、視線や姿勢、ジェスチャーといった非言語的な部分は、AIにはまだ汲み取りきれない機微があるため、プロのコンサルタントである私が評価します。 そして、話の構成や言葉選びといった言語的な部分は、まずAIが客観的なデータを分析し、その上で私が『相手にどう伝わるか』という戦略的な視点で評価を加えるんです」
彼は続けた。 「真田さんの場合、ご自身の成功体験を語る際、無意識に断定的な表現が多くなり、声のトーンが少し高圧的になる傾向が見られました。これが『柔軟性に欠ける』という印象に繋がっている可能性があります。そして『Whatを語りすぎる』という点。真田さんは『何をしてきたか』を非常に詳細に、専門的に語られます。しかし役員層が知りたいのは、その経験を使って『なぜ』自社に貢献できるのか、会社の未来という『Why』の視点なのです」
返す言葉もなかった。薄々感じていたことを、AIの客観的データとプロの視点から、容赦なく、しかし明確な言葉で突きつけられた。私は自分の経験という名の鎧を着込み、それをひたすら見せびらかしていただけだったのだ。
「真田さん、あなたの経験は間違いなく一級品です。ただ、それを伝える『翻訳機』が、少しだけ古いモデルになっているだけです。一緒に、最新のバージョンにアップデートしませんか?」
中島さんの言葉に、迷いは消えた。私は「AI×ロープレ 面接突破サポートプログラム」への参加を即決した。書類の再構築から始まり、いよいよプログラムの核心である、面接のロールプレイングが始まった。これが、私の価値観を根底から覆す経験になるとは、この時の私はまだ知らなかった。
第三章:鎧を脱ぐ
ロールプレイングは、想像を絶するほど過酷で、そして実り多いものだった。私たちは「応募者役」「面接官役」「観察者役」の三つの役割をローテーションで担当した。
参加者は私を含めて4人。大手IT企業の課長だった男、化学メーカーの次長だったという人物…。皆、私と同じ50代の、それぞれの分野で経験を積んできた男たちだ。役職こそ課長・次長クラスだが、その目にはギラギラとした、それでいて切実な光が宿っていた。彼らの自己紹介や議論の端々から、現状を打破しようとする凄まじいエネルギーが伝わってくる。不思議なものだ。残念ながら私の勤めていた会社では、課長・次長クラスでそのような熱を感じる人物には出会えなかった気がする。これが会社という看板を外し、身一つで勝負をかける姿なのだろうか? 私も彼らに負けてはいられない。自然と背筋が伸びる思いだった。
最初に応募者役を務めた時、私は生まれ変わった職務経歴書を手に、自信満々で臨んだ。しかし、面接官役の、あの元IT課長から、鋭い質問が飛んでくる。「真田さんのご経験は素晴らしい。しかし、それはあくまで前職での成功ですよね? 環境の違う当社で、同じように成果を出せる保証はどこにあるのですか?」
私はムキになって反論した。「私のマネジメント手法は普遍的なものです。どんな組織でも…」
その時、観察者役だった中島さんが静かに口を挟んだ。「ストップ」。再生された自分の姿を見て、私は愕然とした。眉間にしわを寄せ、腕を組み、明らかに不快感を露わにしている。これでは、まるで尋問に答える容疑者だ。
衝撃的だったのは、面接官役を経験した時だ。応募者役の化学メーカーの次長が、滔々と過去の武勇伝を語り始めた。大規模なプラントの立ち上げを指揮した話、難航した海外企業との提携をまとめた話。すごい人なのはわかる。だが、正直、話が長い。「で、結局、うちの会社で何をしてくれるんですか?」と喉まで出かかった。その瞬間、ハッとした。
「ああ、そうか…」
思わず声が漏れた。面接官たちは、こんな気持ちだったのか。私の話を、こんな風に聞いていたのか。背筋が凍るような思いだった。初めて、私は「相手の視点」というものを、腹の底から理解した。
セッションを重ねるうちに、私は自分の「鎧」を一枚、また一枚と脱ぎ捨てていった。年下の面接官を見下す気持ちも、自分の経験をわかっててもらえない苛立ちも、すべては自分の弱さの裏返しだったことに気づいた。
特に重点的に訓練したのは、シニア層が必ず聞かれる「懸念事項」への回答だった。「年下の上司と、うまくやっていけますか?」という質問に対し、中島さんは私にこう問いかけた。
「真田さんにとって『尊重』とは何ですか? 年齢ですか、それとも役割ですか?」
その問いに、私は深く考えさせられた。そして、中島さんと一緒に作り上げた回答は、単なる言い回しではなく、私の哲学そのものになった。
「はい。むしろ、私にはない視点や新しい価値観を、ぜひ学ばせていただきたいと思っています。年齢に関わらず、その役職を担われている方の知見は尊重すべきものです。私は、これまでの経験で培った調整力やリスク管理能力でチームをサポートし、その方のリーダーシップが最大限発揮されるよう貢献したいと考えています」
プライドではなく、「人間的成熟度」。経験を誇示するのではなく、新しいことを学ぶ「学習意欲」。私が示すべきは、それだったのだ。
最終面接を想定した「ハイステークス・シミュレーション」は、さらに実践的だった。「当社の主力事業が、5年後に海外の安価な製品にシェアを奪われるという予測があります。あなたなら、技術部門の責任者として、どのような手を打ちますか?」といった、答えのない問いが飛んでくる。過去の実績を語るだけでは、到底太刀打ちできない。企業の公開情報や業界レポートを読み込み、自分なりの仮説を立てて臨む。仲間たちと議論を重ねる中で、私の思考は、一担当者の「How」から、経営層の「Why」へと確実にシフトしていった。
最後のセッションの日、中島さんが私に言った。「真田さん、もう大丈夫ですね。今のあなたは、過去の経験を未来の貢献に繋げることができる、しなやかで意欲的なプロフェッショナルです。自信を持って、行ってきてください」
画面越しの彼の笑顔に、私は深く、深く頭を下げた。
第四章:未来への扉
そして、運命の日がやってきた。志望していた、電子部品業界向けのコンサルティング・プロジェクトマネジメント職の最終面接。役員会議室の重厚なドアを開けると、そこには私より10歳は若いであろう3人の役員が座っていた。以前なら、それだけで身構えていただろう。だが、今の私は不思議なほど落ち着いていた。
面接は、穏やかな雰囲気で始まった。私の経歴書に目を通した役員の一人が、口火を切った。「真田さんは、これまで数多くの製品開発をリードしてこられたのですね。特にこの、コストを15%削減されたプロジェクトについて、もう少し詳しくお聞かせいただけますか?」
かつての私なら、「はい、それは私がですね…」と自分の手柄話から始めていただろう。しかし、今の私は違った。
「ありがとうございます。このプロジェクトの成功要因は、私個人の力というより、チーム全員で『なぜコスト削減が必要なのか』という目的を共有できた点にあります。当時の状況として、市場の価格競争が激化しており、このままでは事業の存続が危ぶまれるという危機感がございました。そこで私は、単にサプライヤーに値下げを要求するのではなく、設計思想そのものを見直すことをチームに提案しました。結果として、メンバーから革新的なアイデアが生まれ、目標を大きく上回る成果に繋がったのです。この経験から、個々の技術(What)よりも、チームの向かうべき方向(Why)を示すことの重要性を学びました」
私は、自分の功績ではなく、得られた学びと、それを今後どう活かせるかを語った。役員たちの頷きが、以前とは明らかに違う、深い納得感を伴っているのが見て取れた。
そして、面接の中盤、核心的な質問が飛んできた。 「真田さんほどの経験をお持ちの方ですと、我々のような若い経営陣の下で働くことに、やりにくさを感じることはありませんか?率直にお聞かせください」
来たな。私は心の中で頷き、一度、穏やかに微笑んでから口を開いた。練習した、しかし今は完全に自分の血肉となった言葉を、丁寧に紡いでいく。
「おっしゃる通り、私には30年の経験があります。しかし、それは同時に30年分の固定観念を持っているということかもしれません。だからこそ、私にはない視点や新しい世代の価値観を、ぜひ皆様から学ばせていただきたいのです。年齢に関わらず、その役職を担われている方の知見を尊重し、チームの一員として貢献することに、何の抵抗もありません。むしろ、これまでの経験で培った調整力でチームをしっかりとサポートし、皆様のリーダーシップが最大限発揮されるよう、黒子に徹することもできます」
私の答えに、3人の役員が顔を見合わせ、深く頷いたのがわかった。彼らが抱いていたであろう最後の懸念が、氷解していくのが空気で伝わってきた。
面接の最後、「何か質問はありますか?」と問われた。これも準備通りだ。
「はい、一つだけ。このポジションで最も早く成果を上げている方に共通する特徴や、行動様式のようなものがあれば教えていただけますでしょうか。入社後、一日も早く貴社に貢献するための参考にさせていただきたく存じます」
私の質問に、中央に座っていた社長の目が、初めて興味深そうに細められた。それは、私を「評価される側」から、「共に働く仲間」として見た瞬間のように感じられた。
面接室を出た時、私には確かな手応えがあった。合否はわからない。だが、自分の持つ全てを、最高の形で伝えきったという清々しい満足感があった。
三日後の夕方。見慣れない番号からの着信に、私の心臓が大きく脈打った。
「真田慎二様の携帯電話でいらっしゃいますか?」 「はい、真田です」 「わたくし、株式会社〇〇の…」
内定だった。
電話を切った後、私はしばらくその場に立ち尽くした。じわじわと、体の奥底から喜びが湧き上がってくる。リビングへ行くと、明子が心配そうな顔で私を見ていた。私が黙って親指を立てると、彼女の顔がパッと輝き、「よかった…!本当に、本当によかったわね!」と涙ぐんだ。
今回の転職活動は、単に新しい職を見つけるためのものではなかった。53年間、自分が築き上げてきた「真田慎二」という人間を一度分解し、客観的に見つめ直し、そして未来に向けて再構築する、壮大な旅だったのだ。プライドという重い鎧を脱ぎ捨て、それをしなやかな自信へと作り変えるプロセスだった。
来週から、新しいキャリアが始まる。そこには、また新たな困難が待ち受けているだろう。だが、今の私には、それすらも楽しみに思える。なぜなら私は、過去に固執するのではなく、未来を創るために経験をどう活かすかを学んだのだから。
窓の外に広がる夕暮れの街を眺めながら、私は深く息を吸い込んだ。ラストワンマイルの向こうには、まだ見たことのない、新しい景色が広がっていた。