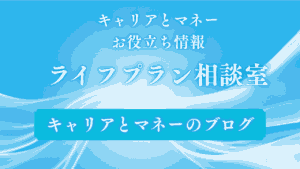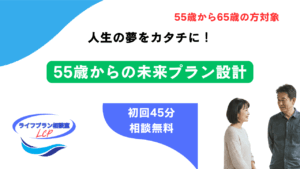キャリアを重ねた今だからこそ必要な、「自分」を見つめ直すための徹底解説
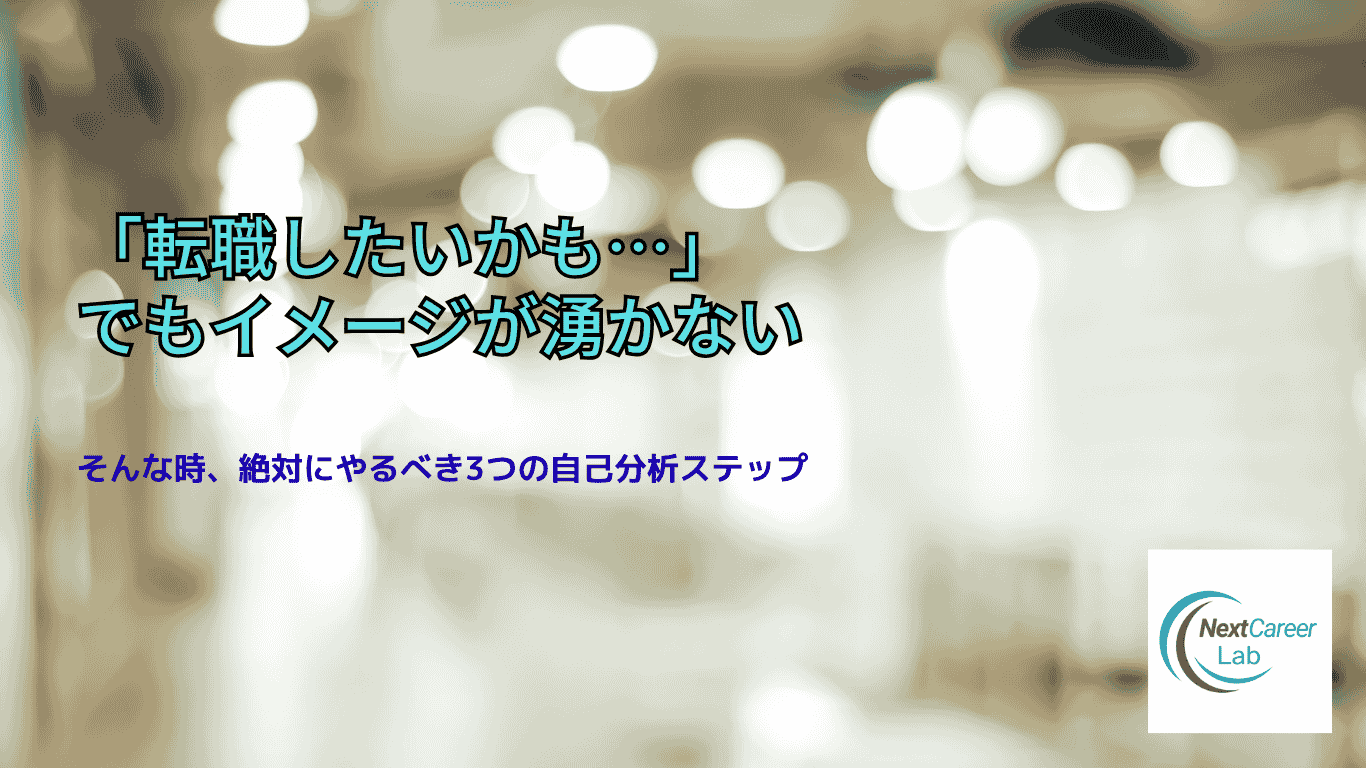
「最近、今の会社にこのままいていいんだろうか…」
「周りも転職し始めたし、自分も考えたほうがいいのかもしれない」
そんな風に、漠然と「転職」という二文字が頭をよぎること、ありませんか?
でも、いざ「じゃあ、どんな会社に行きたいの?」「あなたの強みって何?」と自分に問いかけてみても、スッと言葉が出てこない。 今の仕事に大きな不満があるわけじゃないけど、かといって燃えるような情熱もない。 自分に市場価値があるのか不安だし、そもそも何ができるのかもよくわからない。 どんな働き方がしたいのか、何を優先したいのかも曖昧なまま…。
こんな風に「転職を考え始めたけど、具体的なイメージが全く湧いていない」状態を、私たちは「モヤモヤ期」と呼んでいます。
このモヤモヤ期に、多くの人が焦りを感じてしまいます。 「早くしないと年齢的に厳しくなる」「とりあえず情報収集だけでも」と、慌てて転職サイトに登録し、目についた求人になんとなく応募してしまう。
でも、ここに一つ、落とし穴があるんです。
転職活動を成功させるには、まず「自分は何者で、何を大切にし、どこへ行きたいのか」という根本的な問いに、あなた自身が答えることが不可欠です。
この土台が曖昧なままだと、焦って情報収集や求人応募に進んだ結果、「間違った選択をしてしまうんじゃないか」という不安がどんどん大きくなり、活動が止まりがちになります。面接でうまく自己PRができず、お見送りが続き、次第に「やっぱり自分には無理なんだ」と自信を失ってしまう…そんな負のループにハマってしまう方も少なくありません。
特に、私たちのようにキャリアを重ねたミドル・シニア層の場合、その悩みはさらに深くなります。 転職の動機は、若い頃のように「給与アップ」や「キャリアアップ」といった単純なものだけじゃないですよね。「これまでの経験をどう活かすか」「キャリアの集大成として何を成し遂げたいか」「組織への貢献か、個人の充実感か」といった、いろんな思いが絡み合ってきます。
だからこそ、イメージが湧いていない初期段階において、誰よりも深く自分を理解しておく必要があるんです。
この記事では、そのモヤモヤした「イメージが湧かない」状態から抜け出し、確かな一歩を踏み出すために不可欠な「3つのこと」を、具体的な方法論と共にていねいに解説していきます。 これは、小手先のテクニックではありません。あなたのキャリアの「土台」をもう一度しっかり見つめ直す、最も重要で本質的な作業です。
読み終わる頃には、あなたはご自身の「現在地・価値観・目的地」を自分の言葉で話せるようになり、自信を持って「戦略的な転職活動」のスタートラインに立てるはずです。
あなたは「何者」か?
まずは「経験・スキル・実績」の棚卸しから
転職活動の出発点、それは「客観的に自分を理解する」ことです。 イメージが湧いていない段階では、「自分には何もない」なんて思いがちですが、それは違います。まずは「自分は何ができるのか」を具体的に把握することが、自信や方向性を生み出すための最初の燃料になります。
このステップで行うのは、過去の経験から得た強みや弱み、そして具体的な実績を徹底的に整理する「キャリアの棚卸し」です。
よくある誤解:「棚卸し」=「職歴の羅列」ではない
多くの人が、棚卸しと聞いて「〇〇会社 営業部 3年」「××会社 企画部 5年」といった職歴をただ並べることだと誤解しています。 でも、それではあなたの「価値」は全く伝わりません。重要なのは、その環境で「何を考え」「どう行動し」「どんな成果を出したか」という、その中身そのものなんです。
📝 棚卸しの具体的な進め方
A4のコピー用紙でも、ExcelやNotionでも、何でも構いません。まずはあなたの頭の中にある情報をすべて書き出すことから始めましょう。
1. キャリアの「事実」を時系列で書き出す
新卒(あるいは最初のキャリア)から現在に至るまで、以下の項目を時系列で書き出してみましょう。
| 時期 | 所属 | 役割・役職 | 主な業務内容 | ツール・スキル |
|---|---|---|---|---|
| 2010年4月〜 2015年3月 |
〇〇株式会社 営業推進部 |
メンバー → サブリーダー |
|
Excel (VLOOKUP, ピボット), PowerPoint, Salesforce (入力程度) |
| [次の時期] | [次の所属] | [次の役割] | [次の業務内容] | [次のスキル] |
これを、現在までのすべての部署・プロジェクト単位で書き出します。
2. 「実績(成果)」を定量情報で補強する
次に、書き出した「業務内容」に対して、「どのような成果(実績)を出したか」を追記します。ここでの鉄則は、「具体的な数字」(定量情報)を用いることです。 なぜなら、数字は「客観的な説Duke力」を持つからです。
| NG例 | OK例 |
|---|---|
| 売上アップに貢献した。 | 新規開拓リストの精査とアプローチ手法の見直しを提案・実行。担当エリアの売上を前年比125%(8,000万円→1億円)に引き上げた。 |
| 業務を効率化した。 | 請求書発行プロセスを見直し、RPAツールを導入。経理部門の月間残業時間を平均20時間削減した。 |
| マネジメント経験がある。 | 5名のチームをマネジメント。週1回の1on1を実施し、チームの離職率を20%から0%に改善し、部署のMVPを2期連続で獲得した。 |
もし「自分は事務職だから数字なんてない」と思っても、諦めないでください。「削減した時間」「改善した%」「短縮した日数」「対応した件数」など、必ず数字にできるものがあります。
3. 「スキル」を抽出する(テクニカル vs ポータブル)
書き出した業務内容と実績から、あなたが持つ「スキル」を抽出します。スキルは2種類に分けて考えると整理しやすくなります。
① テクニカルスキル(専門スキル)
特定の職種や業界で必要とされる専門知識や技術。
(例:Python, Java, 高度なExcel, SEO, 広告運用, 法務知識, 月次決算)
② ポータブルスキル(持ち運び可能なスキル)
業種や職種が変わっても通用する、汎用的な能力。
(例:課題発見・解決力, ロジカルシンキング, 交渉・調整力, マネジメント, リーダーシップ)
特にミドル・シニア層の転職では、この「ポータブルスキル」がいかに高いレベルで発揮されてきたかが重視されます。
4. 「強み」と「弱み」を分析する
ここまで書き出したリストを眺めながら、「特にうまくいったこと(=強み)」「苦労したこと(=弱み)」を分析します。
- 強み: 成果が出た(数字にできた)業務は、あなたの強みが発揮された可能性が高いです。「なぜうまくいったのか?」を深掘りします。
(例:売上UP → 表面的な強みは「提案力」。深掘りすると「顧客の潜在ニーズを引き出すヒアリング力」や「粘り強い交渉力」が本質的な強みかもしれない) - 弱み: 苦手だった業務、時間がかかった業務も正直に書き出します。
(例:細かいデータ入力作業が苦手 → 裏を返せば:大局観を持った戦略立案が得意)
弱みは、裏返せば強みであったり、「改善努力中です」とセットで語れたりする、自分を理解する大事なピースです。
💡 客観的な視点を取り入れる
この棚卸し作業、一人でやっていると「こんなの当たり前だ」と思っていることの価値に、意外と気づけないんですよね。
「こんなこと、できて当然だ」
「この実績は、前の会社だから出せただけだ」
そう感じてしまう経験こそ、市場から見れば「非常に価値のある強み」であるケースは少なくありません。
そういう時、おすすめなのが転職エージェントのキャリアアドバイザーとの面談です。 プロの視点からあなたの経歴を深掘りしてもらうことで、「その経験は、〇〇業界では即戦力として評価されますよ」「その実績は、マネジメント能力の高さを示す素晴らしいエピソードですね」といった、客観的なフィードバックを得ることができます。
ステップ1のまとめ
このステップで、あなたは「何者で、何ができるのか(Can)」という客観的な事実(=武器)を揃えることができました。これが、漠然としたイメージを具体化する最初の、そして一番大事な土台になります。
あなたは「何を大切にする」か?
価値観や「ゆずれない軸」をハッキリさせる
ステップ1で「自分に何ができるか(Can)」が明確になりました。 しかし、転職の成功は「Can」だけでは決まりません。「できる」からといって、それが「やりたい」とは限らないからです。
次に重要なのは、「何を大切にしたいか(Value)」そして「何に心が動かされるか(Will/Motive)」という、あなたの内面にある価値観や動機付けの軸を明確にすることです。
なぜ、これが大事なんでしょう?
なぜなら、ここが曖昧だと、転職後に一番後悔しやすいからです。「人間関係や社風が合わなかったらどうしよう…」という、あの大きな不安。それを避けるためにも、自分の価値観を知っておくことが本当に大切なんです。 どれだけスキルが活かせても、どれだけ給与が高くても、あなたの価値観と組織の文化が致命的にズレていれば、いずれ心は疲弊してしまいます。
このステップでは、漠然とした「転職したい」という気持ちを、「〇〇という価値観を満たす仕事を探したい」という具体的な動機に変え、イメージを形作っていきます。
📝 価値観の軸を明確化する具体的な進め方
ここでも、書き出すことが基本です。「なぜ?」を繰り返して深掘りします。
1. ポジティブな経験の深掘り(Will/Motiveの発見)
まずは、あなたの「心が動いた瞬間」を思い出します。
質問: これまでのキャリアで、最も「楽しかった」「充実していた」「やりがいを感じた」瞬間はいつですか?
(例:若手メンバーを指導し、彼が初めて大型契約を取ってきたとき)
深掘り(なぜ?): なぜ、それにやりがいを感じたのですか?
(例:自分のためではなく、人の成長をサポートすることに喜びを感じるから。チームとしての一体感を得られたから)
→ 見える価値観(軸): 「他者貢献」「育成」「チームワーク」
2. ネガティブな経験の深掘り(Valueの発見)
ポジティブな経験以上に重要なのが、ネガティブな経験の振り返りです。不思議なもので、人は「楽しかったこと」より「嫌だったこと」「ストレスだったこと」を分析するほうが、自分が「絶対に譲れない価値観」に気づきやすかったりします。
ストレスの背景を整理する
質問: これまでで、最もストレスが強かった状況、追い詰められた経験は何ですか?
(例:上司の指示が毎日変わり、現場が混乱しているのに、責任だけ押し付けられた)
深掘り(なぜ?): 「なぜ追い詰められたのか?」
(例:理不尽さ、一貫性のなさ、評価の不透明さが許せなかった)
→ 見える価値観(軸): 「一貫性」「論理性」「公正な評価」を自分は重要視している。
避けたい働き方を特定する
上記の振り返りから、「これから避けたい働き方のパターン」を整理してみましょう。これは、次の職場で同じ失敗を繰り返さないための、大事な「転ばぬ先の杖」になります。
(例)避けたい働き方リスト:
- 意思決定プロセスが不透明で、トップダウンが強すぎる組織。
- 個人の成果のみを追求し、チーム内での情報共有や協力がない環境。
- 「やったもん勝ち」で、プロセスや論理性が軽視される文化。
- 深夜・土日対応が常態化している働き方。
3. キャリアの優先順位(軸)を明確にする
ステップ1(スキル)とステップ2(価値観)で出てきた要素をすべて並べ、自分にとって「譲れない軸」は何か、優先順位をつけます。
優先順位付けの例:
例:年収600万円以上、公正な評価制度、リモートワーク可
例:マネジメント経験が積める、社会貢献性の高い事業
例:企業規模、オフィスの綺麗さ
特にミドル・シニア層は、ここで「給与」よりも「裁量権」「後進育成」「ワークライフバランス」といった、キャリアの集大成としての「充実感」に関わる項目の優先順位が上がることが多いです。
ステップ2のまとめ
このステップで、あなたは「何を大切にし」「何に心が動くのか(Value/Will)」という内面の価値観を明確にしました。これが、企業とのミスマッチを防ぐための強力な「羅針盤」となります。
あなたは「どこへ行きたい」か?
これからの「キャリアプラン」を描いてみる
ステップ1で「現在地(Can)」を把握し、ステップ2で「羅針盤(Value/Will)」を手に入れました。 最後に取り組むのは、「目的地(Goal)」の設定です。
自己理解と価値観の軸が明確になったら、その方向性をもとに、中長期的な視点での「キャリアプラン(今後の目標設定)」を具体的に設計します。
なぜ、転職活動の初期段階で、入社後のプランまで考える必要があるのでしょうか? これは、採用する側の視点、特に面接官の不安を取り除いてあげるためでもあります。
中高年の採用で面接官が気になることの一つは、「この人は、うちで長く頑張ってくれるだろうか?」「環境が変わっても、やる気を持ち続けてくれるかな?」という点です。 「今の会社が嫌だから辞めたい」というネガティブな動機だけでは、この懸念は拭えません。 将来の目標設定(キャリアプラン)を明確に語ることこそが、この懸念を払拭し、あなたのキャリアに対する主体性と覚悟を示す上で非常に重要になるのです。
📝 キャリアプランの具体的な設計方法
ステップ1と2で明確になった「自分の強み」と「価値観」をベースに、未来を描きます。
1. 時間軸を設定する
「頑張ります」という精神論ではなく、入社後3年、5年、10年といった時間軸で、具体的にどう貢献し、どう成長したいかを設計します。
短期(入社後〜3年):即戦力としての貢献
(例:入社後1年以内に、持ち前の交渉力を活かして新規チャネルを開拓し、売上X円を達成する。まずは御社の〇〇という領域の知識を徹底的にキャッチアップする。)
中期(3年〜5年):役割の拡大と新たな価値提供
(例:3年後には、プレイングマネージャーとして3〜5名のチームを率いたい。自分の営業ノハウを形式知化し、チーム全体の営業力を底上げする。そのために、コーチングのスキルを身につける。)
長期(5年〜10年):組織の中核としての貢献
(例:5年後には、営業部門の部長として、事業戦略の立案に関わりたい。10年後には、〇〇(価値観)を体現する存在として、次の世代を育成する役割を担いたい。)
2. 「ありたい姿(To Be)」を描く
キャリアプランというと、「部長になる」「年収1000万円」といった役職や年収(To Have)ばかりを想像しがちです。 しかし、ミドル・シニア層のキャリアプランでより本質的に重要なのは、「どのような自分で在りたいか(To Be)」という、もっと長期的で本質的な「ありたい姿」を考えることです。
OK例 (To Be):
5年後、部門の垣根を越えて人を巻き込み、若手からは「あの人のようになりたい」と目標にされ、経営層からは「彼に任せれば安心だ」と信頼される、「組織の結節点」のような存在でありたい。その結果として、部長という役割を担っていたい。
OK例 (To Be):
専門性を常にアップデートし続け、社内で「〇〇の分野ならあの人に聞け」と真っ先に名前が挙がるような、「頼られるスペシャリスト」であり続けたい。そのために、〇〇の資格取得は通過点だと考えている。
この「ありたい姿」は、ステップ2で明確にしたあなたの「価値観(Value)」と深く結びついているはずです。
ステップ3のまとめ
このステップで、あなたは「どこへ行きたいのか(Goal)」を設計しました。これにより、あなたの転職は「ありたい姿」を実現するためのポジティブで戦略的な一歩として再定義されました。
結論:「自分」という土台が固まれば、モヤモヤは晴れていく
「転職したいかも」という漠然としたモヤモヤ期から抜け出すために行うべき、3つのステップをじっくりと解説してきました。
経験・スキル・実績の棚卸し
あなたが「何者」で「何ができるのか(Can)」という客観的な現在地を把握しました。
価値観と動機付けの軸の明確化
あなたが「何を大切にし」「何に心が動くのか(Value/Will)」という、キャリアの羅針盤を手に入れました。
中長期的なキャリアプランの設計
あなたが「どこへ行きたいのか(Goal)」という、未来の目的地を設定しました。
この3つのステップ(=徹底した自己分析)を通じて、あなたはご自身の経験という「資産」を再確認し、それを市場のニーズに合わせて「戦略的に再パッケージ化」する準備が整いました。
もう、あなたは「自分には何もない」「何をしたいかわからない」と悩んでいた、モヤモヤ期のあなたではありません。
「自分にはこういう強みと実績があり、こういう価値観を大切にしていて、将来的にはこういう姿を目指している。だから、御社を志望するのです」
そう語るための、具体的で説得力のある「素材」がすべて揃ったはずです。
この徹底した事前準備によって、初めて「会ってみたい」と思われる応募書類(職務経B歴書など)を作成するための具体的な素材が揃うことになります。
転職活動は、しばしば「航海」に例えられます。 自己分析という土台が曖昧なまま転職活動を始めるのは、地図も羅針盤も目的地も決めずに、荒波に小舟で漕ぎ出すようなもの。「間違ったらどうしよう」と不安になるのも当然です。
しかし、今、あなたは「現在地」「羅針盤」「目的地」を明確にしました。 この強固な土台さえあれば、これから先にどんな情報(求人)に出会っても、他人の評価に惑わされても、あなたが「間違った選択」をすることはありません。
イメージが湧かないと立ち止まっていた時間は、決して無駄ではなかったのです。それは、あなたらしいキャリアを築くために最も重要な、土台作りの時間でした。
自信を持って、あなたの「次の一歩」を踏み出してください。
さあ、次の一歩へ
最後までお読みいただきありがとうございました。 この記事で紹介した3つのステップは、転職活動だけでなく、今の会社でのキャリアを考える上でも非常に有効です。
まずは、週末に2時間だけ時間を取り、カフェや静かな場所で「ステップ1:キャリアの棚卸し」から始めてみませんか?
もし、一人で進めるのが難しい、誰かに壁打ち相手になってほしいと感じたら、私たちのようなキャリアのプロに相談してみるのも一つの手です。「自分の棚卸しを手伝ってほしい」「客観的な強みを教えてほしい」という方は、ぜひお気軽にご相談ください。あなたの「ありたい姿」を言葉にするお手伝いができるかもしれません。